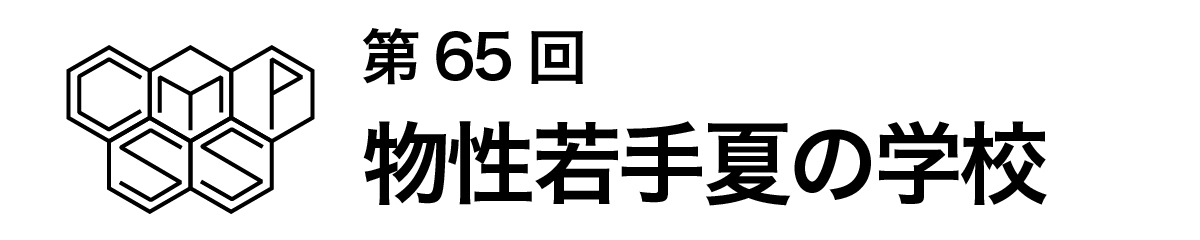集中ゼミ2アブストラクト
超高速構造ダイナミクス計測技術/装置開発のハウツー
羽田 真毅先生(筑波大学数理物質系(エネルギー物質科学研究センター) 准教授)
これまで進められてきた物性研究のほとんどが、物質の静的な構造からその物質の物性との関連を理解するものでした。2000年に入り、安定な極短パルスレーザーが開発されるようになり、超高速構造ダイナミクス計測技術が格段に進歩しました。現在、私たちは物質中の原子位置の小さな変化を直接的に見ることができます。そして、その小さな構造の変化が大きな物性の変化を引き起こすことを知るようになりました。
本集中ゼミでは、物質の光照射によってどのように構造が変化するのか?その構造変化を光・X線・電子線のようなプローブを用いて、どのように観測できるのか?について最近のホットなトピックを紹介しながら議論します。また、余裕があれば、私の開発した超高速時間分解電子線回折装置の設計指針などについて紹介し、装置開発に関して議論したい。
スピン流=電流変換現象の物理
白石 誠司先生(京都大学大学院 工学系研究科 教授)
巨大磁気抵抗の発見以来、スピントロニクスは20年以上物性物理学における大きな注目を集め続けている。第1世代のスピントロニクスでは金属材料を用いた磁気抵抗効果とそれを用いた革新的な素子の研究がその中心的な研究課題であったが、第2世代のスピントロニクスにおいて対象材料のウィングは無機半導体に広がり、希薄磁性半導体の創成など盛んな研究が行われてきた。
21世紀になり、さらによりモダンなスピントロニクス研究として、スピン角運動量の流れであるスピン流の生成・制御を主な研究対象とするスピンカレントロニクスや、固体中の相対論効果であるスピン軌道相互作用を活用したスピン流=電流変換現象の研究であるスピンオービトロニクスが第3世代のスピントロニクスとして大きな脚光を浴びている。これら第3世代スピントロニクスでは、対象材料として、従来の金属材料や無機半導体材料に加え、グラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイドなどの原子膜材料、2次元電子系、金属超薄膜、トポロジカル絶縁体などのエキゾチックな材料が用いられることが多いのも大きな特徴である。
本集中ゼミでは、この第3世代スピントロニクス研究に焦点をあて、特に非保存量であるスピン角運動量を保存量に変換することの基礎・応用両面での重要性も鑑み、スピン流=電流変換現象の物理についてスピン軌道相互作用の意味からスタートして最先端の研究成果までを、対象材料の物性にも触れながら包括的・体系的に紹介・議論したい。
磁性理論と高温超電導
上田 和夫先生(東京都立大学 客員教授 / 東京大学物性研究所)
磁性物理と超伝導はともに電子間の相互作用が本質的な役割を果たしている多体電子系が示す現象である。しかし、通常の超伝導に関するBardeen, Cooper, SchriefferによるBCS理論が完成した1957年以降しばらくの間は、これら二つの研究分野はほぼ独立と考えられていた。磁性現象の源が電子間の斥力相互作用に起因するのに対して、超伝導の本質は電子格子相互作用を媒介とする電子間の実効的引力にあると考えられるからである。斥力による超伝導・超流動の探索は 3 Heの超流動の問題に始まり、重い電子系の超伝導を経て高温超伝導の理解の問題へと受け継がれている。
この集中ゼミでは、磁性絶縁体を記述する有効モデルであるハイゼンベルグ模型に基づく磁性理論から出発する。次いで遍歴電子系の磁性を記述するハバードモデルに対する分子場近似の復習を通じて金属磁性理論の理解にはスピンのゆらぎの効果を取り入れることが重要であることを紹介する。スピンのゆらぎを取り入れた磁性理論の構築はまだまだ発展途上にあると言わなければならないが、強磁性あるいは反強磁性量子臨界点近傍では比較的整備された理論体系が存在する。
量子臨界点近傍では量子ゆらぎのために金属であるにもかかわらず非フェルミ液体的性質を示し、高温超伝導体の特異な性質と考えられているものが、それによって理解されることを紹介する。
生化学反応の数理~分子の状態・形・数の問題
冨樫 祐一先生(広島大学大学院 統合生命科学研究科 准教授)
生物の活動の多くは化学反応によって支えられている。それを反応系・反応拡散系として数理モデル化した研究もまた数多い。生物の形態形成を自発的な空間パターン形成として説明しようとしたチューリングの研究から70年近く、近年も計算機と定量的な実験技術の進歩により発展を続けている。
これらの研究では、多くの場合、化学成分の濃度を変数とした微分方程式(反応速度方程式・反応拡散方程式)が用いられる。この古典的な枠組みでは、分子の状態・個性や、形状・排除体積といった特性は捨象され、また分子は無数にあるものとして連続濃度で表現される。これはマクロな系を考える上では概ね正しいように思われる。しかし、細胞1個の内部といったミクロな領域では、分子の状態や形、また数の有限性が顕わになる場面が想定される。それはどのような効果をもたらすだろうか。
本講演では、生化学反応のモデル化とシミュレーションの手法と実例を紹介した後、主に少数性の問題について、簡単な触媒反応モデルを例に解説する。実際には「状態の問題」「形の問題」「数の問題」は独立でなく、互いに影響しあっている。それが端的に現れる例として、細胞核内のクロマチン構造(DNAがタンパク質との複合体として折り畳まれた構造)に関する最近の研究についても触れたい。
対称性のリソース理論:保存則の元での測定・操作の原理的限界
田島 裕康先生(電気通信大学 大学院情報理工学研究科 テニュアトラック助教)
我々が実行できる操作は、物理法則によってさまざまな制限を受ける。 そうした制限の中でも古くから研究されてきた制限の中に、「保存則が量子的な操作・測定にどのような制限をもたらすか?」というものがある。この問題は測定に関してはWignerが1952年に、操作に関してはOzawaが2002年に始めて提唱した。
現在、こうした問題がリソース理論の視点からrefinementされ、より一般的な「精度とリソースの関係」としてまとめられつつある。こうした理解のもとで、物理量の測定や量子計算(ユニタリー演算)のように一見異なる多くの種類の操作の実行コスト(必要なリソースの量)が、同一形式の漸近等式で記述できることが分かってきた。
この集中ゼミでは、量子情報理論の基本事項・保存則のもとでの測定・操作に関する研究の歴史を概観した後、リソース理論における最新の知見、量子情報理論の各種最新の話題との関連までを一通りまとめる。
測定型量子計算の基礎と応用 -物性物理との関連-
竹内 勇貴先生(NTT コミュニケーション科学基礎研究所 メディア情報研究部 研究員)
量子力学現象を上手く利用することで計算を行うユニバーサル量子計算機は物性物理や量子化学など様々な分野に恩恵を与える可能性があるとして近年、注目を集めている。そのようなユニバーサル量子計算機を実現するための計算モデルとして、これまで様々なモデルが提案されてきた。その中でも、2001年にRobert RaussendorfとHans J. Briegelによって提案された測定型量子計算は、古典計算には対応物が無い量子計算特有のモデルとして盛んに研究されている。測定型量子計算を用いることによって、安全なクラウド量子計算(遠隔地のサーバに計算内容を漏洩すること無く、量子計算を委託する方法)が可能であることを(簡単に)証明出来るようになった。さらに、測定型量子計算が提案されたことによって、物性物理と量子計算の関係性もより深く理解出来るようになった。特に、分配関数と測定型量子計算は密接に関係しており、この関係性を用いることで、量子計算の古典計算に対する優位性を(ある計算機科学的な仮定のもとで)証明することも出来る。この優位性は量子スプレマシーと呼ばれており、最近の量子計算分野のホットトピックの一つである。
本集中ゼミでは、量子計算の簡単な紹介から初めて、測定型量子計算の基礎とその応用、特に分配関数との関係性を用いた量子スプレマシーの証明までを紹介する予定である。量子計算と物性物理がinteractiveな関係にある密接に関連した分野であることが少しでも伝われば幸いである。