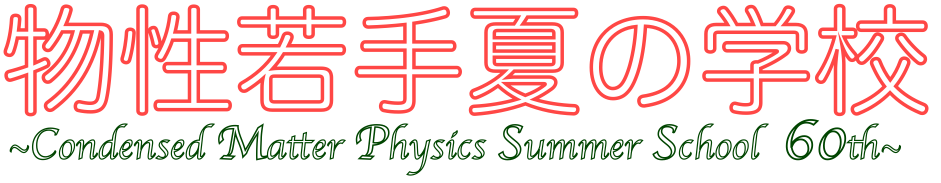
•分科会
▌分科会とは?
学会や研究会などの口頭発表と同じ形式ですので、例えば物理学会の発表練習の場として大いに活用できると思います。
PSと同様、こちらも各会場の一位の発表者にささやかな賞品を進呈する予定です!!
(※注意!)スタッフが適切でないと判断した場合は、賞を出さない可能性があります。
○ 話し手にとって
| 分科会発表 | 学会発表 |
|---|---|
| 研究成果の十分出ていない人も歓迎 | 学会発表に足る成果があることが前提 |
| 自分の好きなように発表できる | 発表内容は指導教官と打ち合わせを重ねる |
| おおざっぱな分野分けなので専門外の聴衆が大半 | 最先端でしのぎを削る研究者が聴衆 |
同じ口頭発表でも学会とはずいぶん違い、あまり緊張せずに発表できると思います。
口頭発表は、短い時間の中でいかに要点をコンパクトに伝えられるかが重要になります。まだ発表経験の少ない人にとって、分科会で発表することは貴重な経験になるでしょう。学会発表へ向けた練習の場として役立つはずです。
もちろん分科会ではPSよりも多くの人に聞いてもらえるため、質疑応答や休憩時間などでより有意義な議論をすることができます。
発表慣れしている方も、自分の研究内容をアピールする場としてぜひ利用してください!
また、学部生やM1でまだ研究のテーマが決まっていない方も、自分が読んで関心を持った論文などのレビューを発表して頂いても構いません。
○ 聞き手にとって
例えば日本物理学会の物性分野は現在12領域(物理教育を除く)に分けられ、発表の際はさらに細かい100を越える分野に分けられています。
それに比べると物性若手夏の学校の分科会はとても大雑把な分け方です。
しかし、物性若手夏の学校の分科会ではこの大雑把さのおかげで若干関わりはあるものの普段聞くことの無い研究に触れることができます。
ぜひ発表している人にいろいろ質問をして、物性物理の面白さを肌で感じてください!
また、分科会招待講演では今をときめく若手研究者の方々に最新の研究成果をお話ししていただきます。
エキサイティングな研究の話を聞けると同時に質疑応答や休憩・食事・懇談会を通じて学会とは全く異なる距離感でお話できるチャンスでもあります。
▌ 分科会の詳細
| 日時 | 7/29 (水) 15:30〜19:00 |
| 発表時間 | 招待講演発表30分+質疑10分、一般参加者10分+5分 |
| 形式 | ファイルタイプは問わず発表スライドを作成して下さい。PCは持参願います。 |
| 発表申し込み | 物性若手夏の学校参加登録時に受付 |
| 注意 |
1. 概要提出期限等についてはこちらを参照下さい。 2. 夏学終了後に受賞者の名前と発表タイトルをウェブページに載せる予定です。 伏せたい方はご連絡ください。 |
▌招待講演講師一覧 (五十音順、敬称略)
| 岡田 佳憲 | 東北大学 原子分子材料学高等研究機構 | 走査トンネル顕微鏡による 遷移金属酸化物薄膜の電子状態イメージング |
| 酒井 志朗 | 理化学研究所 計算物質科学研究チーム | 銅酸化物高温超伝導体の動的電子構造の数値計算 |
| 辰巳 創一 | 京都工芸繊維大学工芸科学部 生命科学物質域 | 単純ガラスの熱容量から見るガラス転移の向こう側 |
| 新見 康洋 | 大阪大学大学院理学研究科 物理学専攻 | スピン流で観る物理現象 |
| 星野 晋太郎 | 東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻 | 多軌道強相関電子系におけるエキゾチック超伝導 |
| 渡辺 宙志 | 東京大学物性研究所 物性設計評価施設 | 大規模計算による非平衡研究の可能性 |
岡田 佳憲 先生 (東北大学 原子分子材料学高等研究機構)
近年、物性研究における走査トンネル顕微鏡(STM)を用いた電子状態イメージングの発展は目覚しく、原子配列の可視化と共にバンド構造を詳細に調べることが可能にな ってきた。このようなアプローチは、銅酸化物高温超伝導体を代表とする複雑な量子 材料を深く理解するうえで極めて重要となる。今まで、STMを用いた電子状態イメー ジングは層状構造を有するバルク結晶を壁開して得られる表面でもっぱら行われてきたが、この手法を壁開では得られない結晶表面で行えれば物性研究の新展開が期待できる。そこで、我々は近年パルスレーザー堆積(PLD)装置とSTMを連結した装置を建設し、原子レベルで制御されたエピタキシャル酸化物薄膜表面の電子状態を 詳細に調べている。
当日は、今までの講演者の研究を例に挙げながらSTMを用いた電子状態研究のアプローチの強みを紹介すると共に、最近の遷移金属エピタキシャル薄膜表面のSTM計測の結果について講演する予定である。
遷移金属酸化物は Fe や Cu といった我々にとってとても馴染みのある元素の酸化物であり、磁性、半導体、超伝導体といった多彩な物性を持っています。この物性を解明することは希土類化合物をはじめとした基礎研究の発展はもちろん、デバイス応用への研究にさらなる拍車がかかるとてもポテンシャルの高い物質だと言えます。
今回、講演を行っていただきます東北大学岡田佳憲先生は表面の電子状態を調べることのできる強力な手法である走査トンネル顕微鏡を用いた電子状態研究を行っています。過去にも光電子分光法を用いた電子状態研究も行っており、電子状態の側面から活躍している若手研究者の一人です。
この分野を初めて聴講する学生の皆さんの「理論だけど実験でどのように電子状態を調べることができるのか知りたい!/レーザーで薄膜をどのように作っているの?/どうして固体表面を調べているの?」といった基本的であるがとても大切な疑問やこの分野で研究している学生の皆さんの「実験データからそのような解釈ができるのか!/理論や他実験の結果とどのように対応しているのか?」といったに疑問に対して、解消ができ、さらに、研究の視野が広がるきっかけになればと思います。
酒井 志朗 先生 (理化学研究所 計算物質科学研究チーム)
銅酸化物の高温超伝導は、母物質のモット絶縁体と高ドープ領域のフェルミ液体的金属の中間に発現するという点で、まさに強相関電子系の問題である。その発見(1986年)は、以来30年近くにわたって、様々な非摂動論的理論手法の発展を促してきた。中でも、銅酸化物の標準模型である2次元ハバード模型のような微視的模型について、数値計算を駆使して相関効果を可能な限り精度よく取り込む計算科学的手法が、計算機性能の向上と共に大きく進展してきた。動的平均場理論とそのクラスター拡張もその一つである。この方法を2次元ハバード模型に適用すると、何らの仮定無しに、反強磁性モット絶縁体相・フェルミ液体相・d波超伝導相及びその高温側の異常金属(擬ギャップ)状態を含む、銅酸化物の相図をよく再現することが知られている。
動的平均場理論の大きな特長の一つは、電子のグリーン関数や自己エネルギーの動的(エネルギー依存)構造を計算できることである。実際、銅酸化物に対応するパラメータ領域の2次元ハバード模型について、それを計算すると他の系では見られない特徴的なピークやギャップの構造が見られる。本講演では、それらの動的電子構造から示唆される高温超伝導機構について、我々が得た結果を中心にこれまでの研究成果について 概観する。特に、超伝導を「高温」にしている隠れたフェルミオン的励起の存在と、擬ギャップと超伝導の関係について、最近得られた結果を紹介する。
動的平均場理論は電子間に働く強い相関効果を扱う上で非常に有効な手法として、この20年来、発展し続けてきました。通常の平均場では無視されている時間的な揺らぎを取り入れる方法で、無限次元において厳密になります。
酒井先生は、この理論をより現実的な系に拡張するという切り口から、様々な強相関電子系の問題に取り組まれています。近年の研究の中で最も注目を浴びているのは、銅酸化物高温超伝導体がなぜ高温なのか、これまでの考えを一新する画期的な成果です。光電子分光法では見ることのできない領域に隠れているギャップの謎にも迫る今回の講演は、必ずや参加者の知的好奇心を満たすものと思います。皆様ふるってご参加ください。
辰巳 創一 先生 (京都工芸繊維大学工芸科学部 生命科学物質域)
“ガラス転移は物性科学の重要な未解決問題である.”このフレーズを物理学者は何度繰り返して来たことだろう.カウツマンによって有名なカウツマンパラドックスが提唱された時から,その文言はほとんど変わってはいない.
何故,ガラス転移がこのように未解決であり続けるのか,その大きな理由は実験による検証の困難さにある.液体を結晶化させることなく急冷し,過冷却液体を経て更に冷却すると,その過程で粘性が急激に上昇し-つまり分子の運動性が失われ-ガラス状態へと遷移する,これがガラス転移であり,実験的には,液体の有する緩和時間が実験時間を越える現象である.従って理論的にその緩和時間の発散的な挙動について予測されても,その発散そのものを実験的に検証することはその定義からほぼ不可能となってしまう.
それでも先人たちはその転移点の手前でガラスに至る直前の過冷却液体がどのように振る舞うのかについて,理論,実験両面から知見を積み重ねて来た.当初は理論で扱う分子はいかにも単純にすぎ,実験で実現されるガラス性物質はあまりにも複雑だった.しかし,近年,我々が行った単純な物質でのガラス転移の実験とそれに伴う解析から,今まで知られていなかったガラス転移直前の過冷却液体に潜む普遍性があることがわかってきた.
本講演では,単純な物質-プロペン-でガラス状態を実現し,そのガラス転移にかかわる熱的な性質について測定することで,見出された普遍性と,ガラス転移温度の向こう側-カウツマン温度-に向かって見出された特異性について発表したい[1].
[1] "Thermodynamic Study of Simple Molecular Glasses: Universal Features in Their Heat Capacity and the Size of the Cooperatively Rearranging Regions", S. Tatsumi, S. Aso, and O. Yamamuro, Phys. Rev. Lett., 109, 045701 (2012)
辰巳先生は、熱容量測定や自発的エンタルピー緩和測定により、単純な物質のガラス転移について研究されています。物質を結晶化させずに冷却させると過冷却液体となり、分子の乱雑な構造を保ったまま流動性を失ってガラス状態になります。これをガラス転移といい、植物の発芽や冷凍食品の保存性など様々な場面で出てきます。
辰巳先生の最近の研究では、細孔凝縮法による極端に単純な分子のガラス形成について研究され、単純な物質を不当凍化し、その熱的な性質を調べられている。単純な物質は普通に冷却すると結晶化してしまうため、直径数nm程度の細孔中に液体を凝縮させ、その閉じ込め効果によって結晶化を阻害する細孔凝縮法によって不凍化を実現されました。
辰巳先生の分科会招待講演では、「単純ガラスの熱容量からみるガラス転移の向こう側」という題で、ガラス転移の世界をご講演いただける予定です。ガラス転移について、詳しく知りたいという方は、ご参加ください!
新見 康洋 先生 (大阪大学大学院理学研究科 物理学専攻)
スピントロニクスとは、電子の持つ電荷とスピンの自由度を組み合わせて、工学的に利用・応用する分野の呼称である。スピントロニクスにおける最も顕著な成功例は、巨大磁気抵抗効果を応用したハードディスクドライブのヘッドで、今日の情報社会で欠くことのできないツールとなっており、巨大磁気抵抗効果を発見したAlbert Fert教授とPeter Grunberg教授には2007年にノーベル物理学賞が授与されている。最近になって、この分野からスピンホール効果やスピンゼーベック効果など新しい現象が報告されており、これらの現象は次世代超低消費電力デバイスへの応用が期待されるため、非常に注目を集め、現在集中的に研究が進んでいる。
これらの現象の起源となるのが、スピン流と呼ばれる、電荷の流れを伴わないスピン角運動量のみの流れである。この特性に着目すると、上記の応用研究だけでなく、物質中のスピン状態を感度よく検出する新たなプローブとして基礎研究にも使用できる。そこで本講演では、まずスピン流の基本的な考え方、生成及び検出方法を紹介した後に、実際に「スピン流で観る」とどんな物理現象が明らかにできるのか、我々が取り組んでいる最新の研究を分かりやすく説明したい。
文字通り、スピンによるエレクトロニクスを意味する「スピントロニクス」という言葉は、私たちにとって既に馴染みの深いものですが、巨大磁気抵抗効果が発見されたことを契機としてこの分野が盛んに研究されるようになってから、未だ30年ほどしか経っていません。数ある物理の分野の中でも新しいものであることもあって、現在もなお、スピンホール効果やスピンゼーベック効果などの新たな現象が発見され、研究も盛んに行われています。その中で、新見先生は次世代のスピントロニクス分野の担い手として活躍されている方であり、スピンホール効果の発現機構やスピン流の緩和機構を明らかにする研究をされています。講演では、スピントロニクス研究の基礎的な部分から、先生が現在取り組んでおられる最先端の研究までお話ししていただく予定です。スピントロニクスを今こそ知りたい!新見先生の研究について伺いたい!という方は是非足をお運びください。
星野 晋太郎 先生 (東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻)
室温以下の固体中では電子が主役を演じている。電子の持つスピンや軌道などの自由度が相互作用によって複雑に絡み合っており、そこから生み出される多彩な挙動を理解することが物性物理学の目的のひとつである。このような電子の集団が生み出す特徴的な物理として、超伝導現象がある。これは電気抵抗の消失や完全反磁性などの著しい性質を示し、応用の観点からも注目を集めている興味深い状態である。超伝導状態は電子対(クーパー対)の量子凝縮状態として理解されている。良く知られたBCS理論では、この電子対はフォノンを介した有効引力によって形成される。一方で電子対を作ることは電子間の斥力が強い系(強相関系)でも可能である。すなわち、空間的に離れた電子対を考えることにより、斥力相互作用エネルギーを損することなく対形成することができる。ここで想像を膨らませると、斥力を避けるために時間も利用できるように思えてくる。こうして時間的に離れた電子対形成(奇周波数超伝導)という考え方に至る。実際、我々は重い電子系と呼ばれる物質群において、この奇周波数超伝導の実現可能性を提案した。理論的にこれを記述するには局所的な電子相関を正確に取り込む必要があり、このような枠組みは動的平均場理論として知られている。講演ではこの理論を多軌道電子系に適用した結果得られた一風変わった超伝導について、最近の進展を踏まえて紹介したい。
超伝導研究の歴史は深く、今から100年以上前に水銀の超伝導状態が発見されて以来、基礎研究及び応用の両面で注目を浴び続けてきました。従来の超伝導状態を記述する理論(BCS理論)では、電子が全スピン及び重心運動量をゼロとするように対を組み、凝縮した状態として、超伝導が説明されました。一方近年では、電子対の全スピンが有限である「スピン三重項超伝導」、電子対の重心運動量が有限である「FFLO超伝導」、そして本講演のテーマでもある、電子対の同時刻相関がゼロとなる「奇周波数超伝導」といったエキゾチックな超伝導の研究が、理論と実験の両サイドから進められています。
星野先生は、強相関電子系、特に重い電子系における理論研究で活躍されている方です。強相関電子系を舞台にして出現する秩序状態やその機構に関して、幅広く研究されています。今回の講演では、奇周波数超伝導についての基礎的な事柄から、関連する最近の研究内容までを紹介していただく予定です。最新の超伝導研究について知りたい方や、一風変わった超伝導に興味がある方は、ぜひご参加ください。
渡辺 宙志 先生 (東京大学物性研究所 物性設計評価施設)
数値計算が実験、理論に次いであらわれた「第三の科学」として扱われるようになってから久しい。計算機の能力も年々向上し続け、それに伴って数値計算を主な研究手法とする、いわゆる「数値計算屋」の数も増えている。一方で計算機を利用した科学のあり方については批判も多い。数値計算では物理の真の楽しさはわからないと主張する理論家もいるし、日本で最も強力な計算機である「京コンピュータ」が、事業仕分けをきっかけに「なぜ必要であるのか」が議論された。現在は「京」のみならずペタフロップス級の計算機が次々と誕生しており、次のエクサスケールに向けて準備が進んでいる。こういった強力な計算機を使って、我々は何を研究すればいいのであろうか?強力な計算機で得られた結果は、本当に人類を賢くしているのであろうか?そもそもそんな強力な計算機を使いこなすにはどうすればいいのだろうか?
本講演では、短距離分子動力学法を題材に、なぜ大規模計算が必要か、最先端のスパコンでどの程度の計算が可能であるか、そして分子動力学法を用いた非平衡研究における今後の課題と展望について述べた後、「はたして数値計算は人類を真に賢くするのか」について皆さんと議論したい。
現在、数値計算は研究の方法として広く受け入れられています。それに伴って、「京コンピュータ」を筆頭に強力な計算機が次々と誕生し、これを用いて、大規模な数値実験が行われています。それでは、最先端のスーパーコンピュータを用いることで、どの程度の計算が可能であり、それは現在の物理研究にどの程度の価値があることなのでしょうか?
本講演では渡辺先生に、短距離分子動力学法を題材として、非平衡研究における大規模数値計算の現状と課題・展望をお話ししてもらう予定です。非平衡系の研究において、なぜ大規模計算を行う必要があるのか?ということから、「京コンピュータ」を用いることでどんな計算を行うことができるのか?ということまで、具体的に解説してもらう予定です。非平衡系の研究に興味のある方や大規模数値計算の現状を知りたい方はぜひ参加してください。