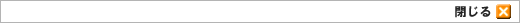
強相関という言葉をご存知ですか?
一度くらいは耳にした事のある方も多いのではないでしょうか。強相関電子系とは物質中で電子間に働く有効的なクーロン相互作用が強いもののことを言います。
武藤先生は動的平均場理論(DMFT)、自己無撞着二次摂動理論(SCSOPT)、密度行列繰り込み群(DMRG)など様々なアプローチで強相関電子系の研究に取り組まれています。今回はその中でも「動的平均場理論から見た近藤効果と重い電子系」というテーマで初学者向けに基礎的な話をしていただきます。また、前半のテーマであるHubbardモデルは目にする機会が多いのではないでしょうか。これらをきちんと理解することで今後の研究に何かしら役立ててくれればと思います。
また、先生のホームページ内の「物理雑記帳」は一見の価値があると思います。さまざまな物理現象をわかりやすく紹介してくれています。 (世話人:上田)
強相関電子系と呼ばれる研究分野は,固体物性研究の大きな一領域を占めてい て,銅酸化物高温超伝導体や有機超伝導体,重い電子系と呼ばれる物質群,鉄や ニッケルなどの強磁性金属といった特徴的な物性を示す多くの物質が,その研究 対象となっています.強相関電子系は,その名前にあるように,固体中の「電 子」の「相関」効果が「強」い系ですが,そもそも,電子の相関効果とは何か, そして,それが強い系では何が興味深いのかが,一言で説明しにくい上に,研究 対象が広範囲に渡るため,研究の面白さのエッセンスが初学者にうまく伝わりま せん.強相関電子系の多種多様な物質における諸物性を記述するのは,現在の最 先端の研究の目的でもあり,容易ではありませんが,そのエッセンスは,強相関 電子系の様々な研究に顔を出すHubbardモデルと呼ばれる理論モデルに含まれて います.本講義では,Hubbardモデルを通して,強相関電子系のエッセンスを, できるだけ平易に解説したいと思います.
近藤効果と呼ばれる,珍しく日本人の名前がついた物理現象があります.これは 磁性不純物を含む金属に見られる電気抵抗極小効果です.この効果の本質が近藤 問題として広く研究対象となりました.さらにその流れが重い電子系と呼ばれる 興味深い一連の物質群の研究に繋がって現在に至ります.広大な研究領域とその 歴史を全て追うことはできませんが,動的平均場理論という理論的枠組の中で, 近藤効果と重い電子系の繋がりを考えてみようと思います.動的平均場理論は, 格子系における電子相関の問題を,一不純物系での電子相関の問題,すなわち近 藤問題に還元して取り扱います.格子系の電子相関の問題の典型例として重い電 子系を考えれば,近藤効果と重い電子系の繋がりの一つの側面を見ることができ ます.本講義では,動的平均場理論を用いて,重い電子系の磁性イオン希釈実験 に対応するモデル計算を行った結果を紹介し,動的平均場理論から見た近藤効果 と重い電子系の関係を考察します.