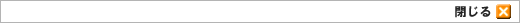
結晶中の電子状態はバンドを作り、絶対温度でそのバンド底から全電子を詰めたエネルギー位置がフェルミ準位である。電気伝導や磁性などの金属物性は、このフェルミ準位における電子の振る舞いで支配され、その運動は波数空間(逆格子空間)におけるフェルミ準位の等エネルギー面、フェルミ面で決まる。物性が分かるということはこのフェルミ面を理解すると言っても過言ではなく、そんなフェルミ面研究は俗にフェルミオロジーと呼ばれている。 さて、固体物理の教科書の名著、AshcroftとMerminの「Solid State Physics」[1]によると、このフェルミ面を測る方法には主にde Haas Alphen効果やShubnikov de Haas効果などの磁気量子振動を利用する。一方、最近では光電効果やトンネル効果、さらには陽電子消滅などを利用した新しいフェルミ面決定法が続々開発され、特に角度分解光電子分光法は直接フェルミ面をマッピングできる強力な手法である。 本セミナーでは、このフェルミオロジーをフェルミ面の基礎から、最近の測定技術、さらに最先端のフェルミ面研究を詳細に説明する。取り上げる主な物質系は、固体表面上の原子細線、金属単原子層、量子薄膜で、これら原子レベルの大きさしかない物質における低次元特有の物性(パイエルス転移など)とフェルミ面の関係について実験結果を踏まえて解説する。
[1] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics (Thomson Learning, 1976) 実は表紙はフェルミ面である。
近年、半導体基板上で繰り広げられてきた回路素子の微細化技術は着実な進歩を遂げ、そのスケールがナノメートルに達した現在では”ナノテクノロジー”と呼ばれている。 この技術発展も最終的には半導体基板上の原子第一層まで到達することが期待されるが、固体基板上の物質が原子厚まで薄くなったときの様子自体は、古くから”表面科学”として研究が行われてきた。結晶表面では表面及び吸着原子が自己組織化して単原子層、原子鎖、ナノドットなどを形成し、様々な低次元量子物性を発現する。 これら表面上の原子構造体内の電子の電場応答は大変興味深い固体物理研究テーマであり、さらに現代エレクトロニクスの究極の回路素子としての可能性を秘めている。 そこでこのような原子レベルに小さいものを実際に電気抵抗測定するために、最近様々なプローブが開発されてきた。例えば、リソグラフィー技術で半導体を削ったもの、原子分解能のあるトンネル顕微鏡の探針を独立に動かすもの、そしてカーボンナノチューブをプローブにしたものなど。本セミナーではこれら最新のプローブとそれを用いた実際の測定を紹介し、さらに実験結果から表面上の原子構造体の電子輸送現象について解説する。
参考:解説「単原子ステップを通過する表面自由電子」松田巌、保原麗、長谷川修司、日本物理学会誌2007年2月号92頁 [日本物理学会誌Vol.62(2), 92 (2007)].